
近年、退職代行やリベンジ退職といった退職の多様化が注目を集めていますが、そのなかでも特に企業に影響を与えているのが「静かな退職」です。
静かな退職とは、会社を辞めずに最低限の業務しか行わない状態を指し、放置すると組織の活力を大きく損なう要因となります。
本記事では、静かな退職が広がった背景や、その兆候を見極めるポイント、さらに企業が取るべき具体的な対策を解説します。
1.今増えている『静かな退職』とは

退職代行の利用やリベンジ退職など、退職の形も多様化しています。
そんななか、話題になっているのが「静かな退職」です。
静かな退職とは何か知らない方のために、その概要を解説します。
- 最低限与えられた仕事をこなすだけの状態のこと
- 退職はしていないものの「離職のリスク」が高い
- 静かな退職とサイレント退職の違い
(1)最低限与えられた仕事をこなすだけの状態のこと
静かな退職とは仕事に対して熱意をもたず、与えられた仕事だけを最低限の力でこなす状態のことです。
この言葉は2022年にアメリカのキャリアコーチ「ブライアン・クリーリー」氏がSNSで発信し、多くの若者から指示されました。
静かな退職者は事実上会社に在籍しているものの、生産性を上げる努力や他の人を率先して手伝う姿勢などがみられません。
出世したいなどの上昇志向もなく、ただ毎日会社に出社して定時で帰宅し、イベントごとなども参加しないような社員です。
このような様子から実質辞めているようなものであるとして、静かな退職と呼ばれています。
(2)退職はしていないものの「離職のリスク」が高い
静かな退職は会社を辞めているわけではありませんが、退職のリスクが極めて高い状態といえます。
なぜなら静かな退職を選んでいる人は会社に対して期待は一切なく、すでに心理的には会社から離脱しているとも言えます。
「退職して新しい仕事を探すのも面倒」「それなら今の会社で、最低限の力で仕事をしておこう」程度の気持ちしかなく、もしも好条件の仕事が舞い込めば簡単に会社を辞めてしまうでしょう。
(3)静かな退職とサイレント退職の違い
静かな退職と似たサイレント退職という言葉があります。
サイレント退職とは兆候なくいきなり辞めてしまうことを意味する言葉で、事前に周囲への相談などもなく退職することです。
静かな退職は会社にいるが辞めているような状態を意味するので、この2つは全く別の意味となります。
2.なぜ「静かな退職」が広まったのか?

静かな退職を選ぶ会社員はここ数年で若年層を中心に増えてきています。
なぜ仕事への意欲を無くしてしまう人が増えたのか、その背景を理解しましょう。
- 労働人口が減少して人手不足になったこと
- 働き方への意識の変革
- リモートワークの広がり
(1)労働人口が減少して人手不足になったこと
静かな退職が増えたのは、企業が人手不足となり、以前ほど人材同士での競争がないことが原因と推測されます。
今の就職市場は売り手優位であり、働き手は「仕事は探せばいくらでもある」と無意識に思っている状態です。
そのため、1つの会社で実力を示して認められるために以前ほど必死になる必要はなく、最低限の力で一定の給与をもらった方が「楽」という考え方が広まっています。
(2)働き方への意識の変革
昭和や平成の時代には、会社員は自分の給与以上の働きをし、会社に還元するものという考えがありました。
そのため社員は会社が終わってからも家に仕事を持ち帰り、休日返上で働くようなこともありました。
しかし、令和の時代になり「プライベートを犠牲にしてまだ働く意味がない」「仕事だけが人生ではない」という多様な価値観が広まりつつあります。
これにより、前ほど熱心に仕事をする姿勢をもたない人が増えたと考えられるでしょう。
(3)リモートワークの広がり
リモートワークの広がりも、静かな退職を後押ししたと推測できます。
働く場所や時間帯にとらわれない柔軟な働き方が選択肢に現れたことで、以前よりも会社への帰属意識を感じる機会が減ったと考えられるためです。
さらに、リモートワークは対面のコミュニケーションがなく、仕事の成果のみで評価されやすいためプロセス評価が難しい状態です。
人によっては「頑張っているのに評価されない」「自分が成長しているかわからない」と不安を覚える社員も少なくありません。
このような新しい働き方の選択肢が会社員の帰属意識の低下や、会社の体制や評価への不満を引き起こし、静かな退職を選ばせている可能性があります。
3.静かな退職を選ぶ人の特徴

企業側としては静かな退職を選ぶ人をいち早く見つけ、モチベーションや帰属意識を持ってもらうような対策が必要です。
しかし一番難しいのが、静かな退職を選んでいる人を見分ける方法です。
まずは静かな退職を選ぶ傾向にある人の特徴を知り、判別の参考にしてください。
- 仕事へのモチベーションが低下している人
- 40〜50代でキャリアへ諦めを感じている人
- 失敗を恐れる傾向にある人
- ワークライフバランスを重視するタイプの人
- 自己実現を仕事に求めない人
(1)仕事へのモチベーションが低下している人
仕事に対する興味や関心が薄れている人は、静かな退職を選びやすいです。
そもそも静かな退職は、「仕事へのモチベーションはないが辞めるのも面倒」という状態であり、明らかにやる気を失っている人は静かな退職状態に足を踏み入れているといえます。
「頑張っても報われない」「この会社で成長できない」と感じていることが背景にある場合も多いでしょう。
早急にコミュニケーションをとり、モチベーション低下の原因を特定したうえで、問題を解決する必要があります。
(2)40〜50代でキャリアへ諦めを感じている人
役職やキャリアの天井が見えてしまい、昇進や給与アップを望めないと感じている中堅・ベテラン層も静かな退職を選ぶことがあります。
「どうせこれ以上は上に上がれないだろう」と思うとやる気が途絶え、あとは定年退職まで穏やかに過ごせれば良いと割り切ってしまうのです。
特に40〜50代の社員は自分たちの子どもが自立しているなど、家庭や生活が安定していることも多く、「無理をしてまで働かなくても良い」と割り切ってしまうケースも珍しくありません。
この年代の社員はある程度の給与を受け取っているため、生産性の低い静かな退職状態になると、会社にとっても痛手です。
かといって退職してしまえば、業務知識が豊富なベテランを失うことになります。
貴重な戦力として業務に取り組んでもらうためにも、キャリアの先を明示するなどして、やる気を取り戻してもらう必要があるでしょう。
(3)失敗を恐れる傾向にある人
新しいチャレンジを避け、失敗しないことを優先するタイプも静かな退職に陥りやすいです。
責任の大きな仕事や目立つ行動を避け、与えられた仕事だけに専念するスタイルが定着すると、やがて向上心を失ってしまうからです。
特に若年層に多いといわれる傾向にあり、「失敗したら終わり」と思うあまり、難しい仕事へ挑戦できません。
日頃から難しい仕事を避けたり、何かと言い訳が多いようなタイプの社員には、失敗は悪いことではないと理解してもらい、失敗してもフォローする体制を社内で作るような働きかけが必要です。
(4)ワークライフバランスを重視するタイプの人
仕事よりもプライベートを優先する考え方を持つ人も、静かな退職に向かいやすい傾向があります。
これは必ずしも悪いことではありませんが、「仕事は生活のために最低限で良い」と割り切ってしまうと、自然と職場での積極性が薄れていきます。
ワークライフバランス重視の姿勢から仕事を効率化するタイプもいますが、そうでないタイプは仕事量を極力減らす方向で調整しようとするからです。
例えば、同僚が残業していても必ず定時で帰るタイプの人、飲み会や業務外の集まりには頑なに参加しないタイプの人は少し気にかけてあげるべきかもしれません。
(5)自己実現を仕事に求めない人
自分の成長ややりがいを仕事以外の場で得ようとする人も、静かな退職を選びやすい傾向があります。
趣味や副業などに情熱を注ぎ、仕事は「お金を得るための手段」と考えているケースが多いからです。
このタイプは、業務の範囲を広げたり責任ある仕事を任せても、必ずしもモチベーションにはつながりません。
むしろ「会社のために頑張る理由がない」と割り切ってしまうこともあります。
こうした社員にやる気を取り戻してもらうには、会社側が研修や勉強会といった自己成長の機会を提供し、「この会社で働くことで自分の人生にプラスがある」という実感を持ってもらうことが重要です。
キャリアパスを示し、成果に応じてスキルアップできる仕組みを整えることで、少しずつ仕事への意欲を引き出せる可能性があります。
4.中小企業が静かな退職を放置してはいけない理由

中小企業が静かな退職を放置してはいけないのには、以下のような理由があります。
- 根底には会社への不満や不信感がある
- 業務の生産性が下がる傾向にある
- ほかの社員への負荷が増大し、モチベーションを下げるリスクがある
- 優秀な人材が流出してしまう可能性がある
(1)根底には会社への不満や不信感がある
静かな退職を選ぶ背景には、会社への不満や不信感が隠れていることが少なくありません。
「努力しても評価されない」「将来の見通しが立たない」と感じた社員は、次第に意欲を失い、最低限の業務しかしなくなります。
この状態を放置すると、不満を抱えたまま働く社員が増え、社内全体の士気が下がってしまいます。
また、このような不満はおそらく多くの社員が抱えているもののため、放置すると離職率が上がってしまうリスクもあるでしょう。
(2)業務の生産性が下がる傾向にある
静かな退職者は必要最低限の業務しか行わないため、業務の生産性が低下しやすくなります。
1日でこなせる仕事量も最低限のものとなるため、捌ける業務量自体が減ってしまうでしょう。
仮に同じ人件費をかけているにもかかわらず成果は減り、結果として費用対効果が悪化してしまいます。
さらに改善活動や新しい挑戦が行われにくくなり、企業の成長スピードが鈍化するリスクもあるでしょう。
(3)ほかの社員への負荷が増大し、モチベーションを下げるリスクがある
静かな退職者が最低限しか働かない穴埋めを、他の社員が負担することになります。
モチベーションが高く、仕事ができる社員ほどこなせる業務量は多いので、そのような社員に負担が集中しかねません。
このような状態が続くと頑張っている社員の心中は「上長はやる気のない社員に注意もしない、私も褒められるわけではない」と不満だらけになってしまいます。
この不満が最終的な離職やモチベーション低下につながり、さらなる悪循環をうむ可能性も否定できません。
(4)優秀な人材が流出してしまう可能性がある
努力が正当に評価されないと感じた優秀な社員は、より良い環境を求めて転職を検討するようになります。
静かな退職者が増える職場では、モチベーションの高い人材ほど先に辞めてしまう傾向があり、企業の競争力を大きく損なう恐れがあります。
静かな退職者が増える職場で労力をかけて仕事をするよりも、優秀でモチベーションの高い社員が多い職場の方が、働き心地が良いのは当然です。
結果としてモチベーションの低い社員のみが残ることとなり、企業の運営自体が成り立たなくなる可能性もあるでしょう。
5.静かな退職者には「再活性化」と「自然淘汰」の両輪で対応する

静かな退職者に対しては、すべての人を引き戻そうとする必要はありません。
モチベーションの低下が一時的なものや、環境によって回復できる見込みがあるなら、1on1や研修などを通じて再活性化を図ることも大切です。
一方で、挑戦意欲がない、成果も出さない、組織への貢献も見込めないと判断される場合は、評価制度によって自然に淘汰される流れを整えることが重要です。
「頑張る人が報われる」「成果を出せない人は処遇が下がる」という透明な仕組みが整っていれば、静かな退職は結果的に減っていきます。
引き戻すべき人材と、淘汰されるべき人材の線引きを明確にすることが、組織全体の健全化につながるのです。
6.企業が静かな退職者に対して取るべき対策

静かな退職者をゼロにすることだけを目標とする必要はありません。
むしろ一定の離職は組織の新陳代謝として健全に機能します。
重要なのは成果を出す社員が正当に評価され、報われる仕組みを整えることです。
- 静かな退職者を見分けるエンゲージメント調査を実施する
- 従業員の職務や役割を明確にする
- 従業員のキャリアパスや評価制度を明示する
- 優秀な社員が成長できる環境を整える
(1)静かな退職者を見分けるエンゲージメント調査を実施する
静かな退職者を見分けることは難しく、上司の主観だけでは見落としが発生します。
そこで有効なのがエンゲージメント調査です。
匿名アンケートや従業員サーベイを定期的に実施して、以下のような指標をスコアリングします。
- 仕事への満足度
- 上司や同僚との関係
- 評価への納得感
- キャリアの展望
これらをスコア化することで、現場では気づきにくい「離脱予備軍」を早期に発見でき、さらにデータを基に改善すれば、社員の本音に根ざした対策が可能になります。
(2)従業員の職務や役割を明確にする
静かな退職が増える最大の理由のひとつは、成果に見合った評価がされないことです。
パフォーマンスの高い人材が「誰がやっても同じ扱い」と感じた瞬間、やる気は急速に冷めます。
そのためには成果基準を明確にし、信賞必罰を徹底する仕組みが欠かせません。
たとえば、以下のような仕組みを導入すると良いでしょう。
- 2期連続で目標未達なら減給・配置転換
- 目標達成率が高ければ昇給・昇格をスピーディーに実施
こうした制度により、社員は「やれば評価される」「やらなければ淘汰される」という明確なメッセージを受け取り、優秀な人材が報われ、成果を出さない人材は自然に入れ替わる健全な流れが生まれます。
(3)従業員のキャリアパスや評価制度を明示する
評価の納得感を高めるには、「何をすれば評価されるのか」を明示することが不可欠です。
職務記述書を整備し、役割・責任・期待成果を具体的に示すと同時に、昇進ルートや給与レンジを明確化しましょう。
特に、高いパフォーマンスを発揮する社員には、短期間での昇格・昇給や重要プロジェクトへの抜擢といったチャンスを提示すると効果的です。
逆に、挑戦を避け続ける社員には責任を軽減し、成果を出せる場への移動を検討するなど、役割配置を柔軟に実施しましょう。
(4)優秀な社員が成長できる環境を整える
優秀な人材ほど、「成長実感」を求めます。
- 外部研修や資格取得支援
- 社内メンター制度
- 挑戦的なプロジェクトへの参画
以上のような機会を提供し、チャレンジを後押しする環境を整えましょう。
そのうえで、1on1面談や小規模な意見交換会などを通じ、上司・経営層との直接的なコミュニケーションを確保します。
ただし、挑戦する意欲のない社員に過度なリソースを投じる必要はありません。
成果を出す社員を徹底的に支援し、そうでない社員は自然淘汰する仕組みが、組織全体の活力を高めるはずです。
7.静かな退職を防ぐ採用段階での工夫

静かな退職を未然に防ぐには、入社後の定着やパフォーマンス向上を見越したエントリーマネジメントが欠かせません。
まず重要なのが採用者と企業側の価値観の一致(カルチャーフィット)です。
スキルだけでなく、会社の文化や価値観が一致(カルチャーフィット)する人材かどうかを重視する考え方で、面接時には「どんな環境でモチベーションが上がるか」「何に違和感を感じるか」を必ず確認し、働くうえでの価値観のズレを見極めます。
また、入社前に会社の良い面だけでなく、厳しい面も包み隠さず伝え、理想と現実のギャップを埋めます。
例えば一日の業務の流れ、残業の実態、社内の人間関係の特徴を率直に共有することで、入社後のミスマッチを防ぎましょう。
最後に自社がどんな文化を持ち、何を目指し、どんな人が活躍しているのかを明確にすることで、自社に合った人材を自然に惹きつけることができます。
これらをわかりやすく発信し、採用段階でのミスマッチを防ぐのに役立つのが採用革命アニメーションです。
企業の価値観や働き方をビジュアルで直感的に伝えられるため、応募者はリアルな入社後のイメージを描きやすくなります。
まとめ
近年注目を集める静かな退職は、社員が在籍していながら意欲を失い、最低限の業務しか行わない状態を指します。
その背景には、働き方価値観の変化、人材不足による競争意識の低下、リモートワークによる帰属意識の希薄化などがあります。
静かな退職を放置すると、組織全体の生産性低下や士気の低下、さらには優秀な人材の流出といったリスクを招きます。
この状況を打破するには、成果を出す社員が正当に評価され、やる気のない社員は自然に淘汰される評価制度を構築し、組織を健全に循環させることが重要です。
そして、静かな退職をそもそも生まないためには、採用段階でのエントリーマネジメントが不可欠です。
自社の価値観や評価方針を正しく伝えることで、組織にフィットする成果志向の人材を惹きつけられます。
採用革命アニメーションは、そのメッセージをわかりやすく発信し、エントリーマネジメントを後押しする有効な手段となります。
Z世代の採用につながるアニメーション動画の制作・運用なら「採用革命アニメーション®」
採用革命アニメーションは、今年で創業65年目の広告会社である株式会社JITSUGYOが運営する採用に特化したアニメーション動画制作サービスです。
アニメーション制作は参入障壁が低く、社歴が短い会社やシェアオフィスで運営している会社が多いのが現状です。そんな中でも、弊社は2023年で66期目になり一般企業だけでなく、国や地方自治体、大学、著名人といったお客様との取引も多数ございます。
65年以上続く広告会社であり伝えることのプロだからこそ、誇れる実績が多数ございます。65年以上続く広告会社だからこそできる圧倒的なシナリオ作成力で、営業から取材、制作、広告運用まで一気通貫したサービスをご提供いたします。
アニメーションは作って終わりではなく、その後の採用に対して、認知拡大やマーケティング部分までサポートできるのが弊社の魅力です。Google広告公式認定資格保持者も社内に在籍していますので、専門的でより効果的な施策を実施することが可能です。
採用につながるアニメーション制作をご検討中の企業担当者様は、株式会社JITSUGYOが運営する採用革命アニメーション®に、ぜひ一度ご相談ください。
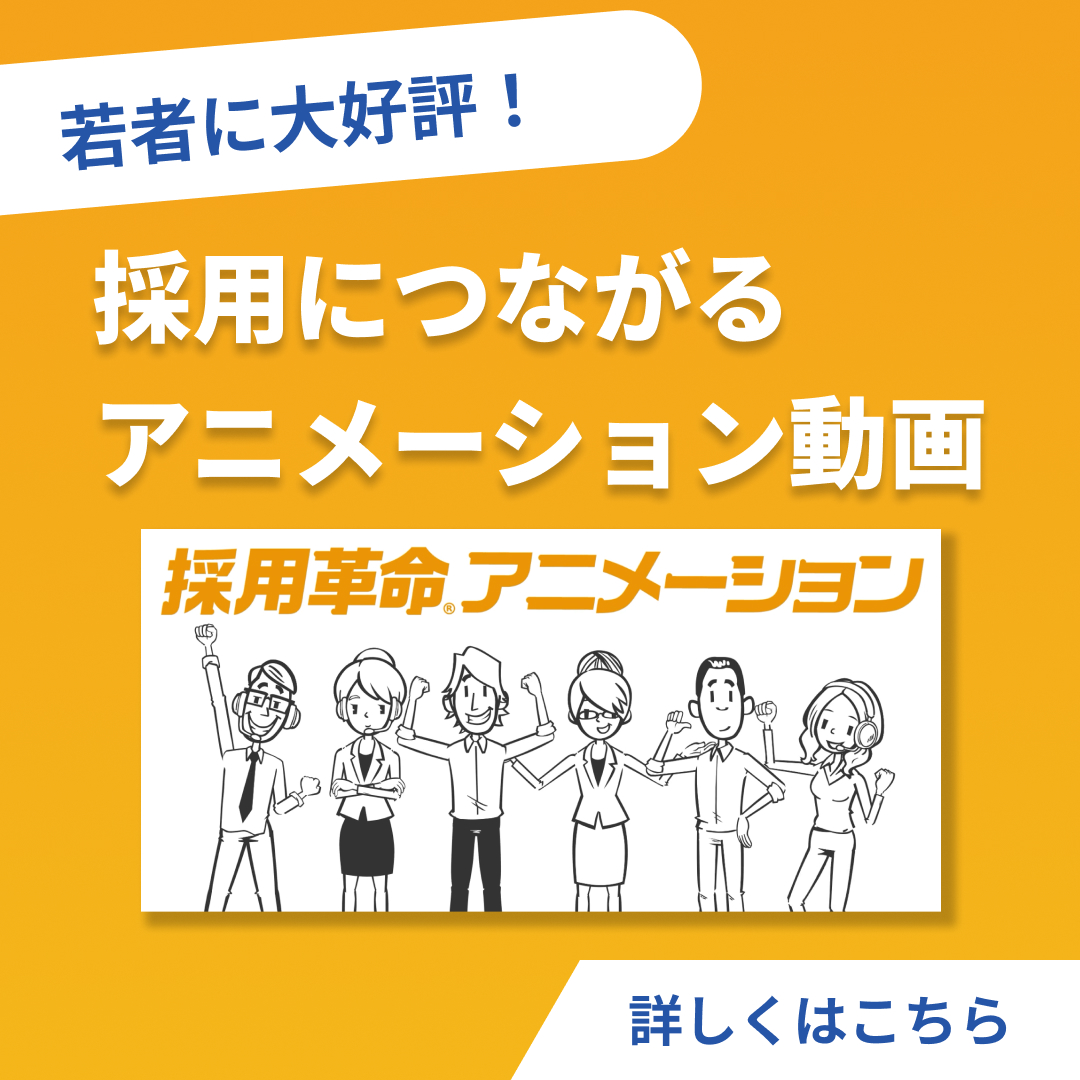

採用革命®アニメーション編集部
年間400本以上の動画制作実績を誇る採用革命®アニメーションの編集メンバー。動画を使ったマーケティングについて、老舗広告会社の視点から解説します。

