
「退職代行サービスの利用者が増えているのはなぜ?」
「どうしたら若者に長く働いてもらえる?」
2025年の新卒入社者の25%が退職代行サービスの利用を検討しているという衝撃的な調査結果が明らかになりました。
昨年比40%増という急増ぶりは、企業の採用戦略に根本的な変革が必要なことを示しています。
本記事では、若者の退職代行サービス利用者が増えた背景と心理を分析し、退職代行利用者を減らすための具体的なアイデアを紹介しています。
1.2025年新卒入社者の4人に1人が退職代行サービスの利用を検討

株式会社NEWONEの調査によると、2025年入社の新卒社員の94.2%が退職代行サービスを認知しており、さらに4人中1人は利用を検討する可能性があると答えています。(出典:「「退職代行を使う可能性がある」と考えている新卒社員は25」)
このアンケート結果を裏付けるように、2025年4月からの1ヶ月で退職代行モームリを利用した人数は、345名にのぼっています。
| 日付 | 2025年度新卒 |
|---|---|
| 4月01日 | 5 |
| 4月03日 | 20 |
| 4月04日 | 13 |
| 4月07日 | 42 |
| 4月08日 | 25 |
| 4月09日 | 20 |
| 4月10日 | 16 |
| 4月11日 | 25 |
| 4月14日 | 38 |
| 4月15日 | 9 |
| 4月16日 | 9 |
| 4月17日 | 14 |
| 4月18日 | 13 |
| 4月21日 | 22 |
| 4月22日 | 9 |
| 4月24日 | 6 |
| 4月25日 | 13 |
| 4月28日 | 16 |
| 合計 | 345 |
なお、2024年4月の利用者は250名であったことを考えると、昨年よりも利用者数が40%も増加しています。
なぜ退職代行の利用者はこのように急増しているのでしょうか。
2.退職代行利用者が急増している背景

退職代行利用者が急増しているのには、以下のような背景があります。
- 退職代行サービスの認知度が上がった
- 退職を後押しするSNSや世間の風潮
- 若年層の自己防衛意識の高まり
- 雇用の流動化
- 退職しにくい企業文化
- 依然残るパワハラやブラック企業の存在
(1)退職代行サービスの認知度が上がった
退職代行利用者急増の背景には、退職代行というサービスの認知度が上がったことが挙げられるでしょう。
退職代行サービス自体は2015年ごろから存在しますが、当初はあまり知られていませんでした。
しかし、翌年にこのサービスの存在がネットで拡散されて徐々に認知度が上がり、2021年以降は退職の選択肢として定着。
2024年ごろからはメディアでも退職代行サービスが紹介されたこともあり、利用者がこの10年で右肩上がりになっています。
(2)退職を後押しするSNSや世間の風潮
最近の世論やSNSではある種、退職を後押しする声が大きくなっており、これも退職代行利用を後押ししていると考えられます。
これまでは「退職くらいは自分で会社に言うべき」「会社をすぐ辞めるのは、悪いことだ」という考えがありました。
しかし、最近は「変な会社だと思ったらすぐに逃げろ」「退職代行を使われるような会社が悪い」というような声が大きくなっています。
このような世論やSNSの声に励まされ、退職代行を利用して会社を辞める人が増えています。
(3)若年層の自己防衛意識の高まり
Z世代の自己防衛意識の高まりも、退職代行利用が増えた要因のひとつです。
SNSネイティブであるZ世代は攻撃的な世論などをネットで多く目にしており、無意識に「間違って叩かれないように黙っておこう」「人と衝突しないようにしよう」と考えています。
さらに、コロナ禍や円安、物価高などの不安定な経済で苦しむ親を見た経験から、「頑張っても報われる保証はない(だったら、自分が楽しく生きていける生活しか望まない)」という価値観が形成されているようです。
このような価値観から、若者は衝突なしにスムーズに退職ができる退職代行サービスを選んでいます。
(4)雇用の流動化
かつての高度成長期のように終身雇用と年功序列による安定した雇用環境と、そそれに伴い、賃金や福利厚生を保証してもらえるような働き方はすでに過去のものとなり、雇用は流動化しています。
このような背景から会社に長く勤め続けることのメリットが薄れ、より良い環境を求めて転職する人が増えています。
「1社に定年まで勤めるのが当たり前」という価値観から、「転職を通じて自分自身のキャリアを築く」という価値観への移行が進んでいるのです。
その結果、退職する人そのものが増え、スムーズに辞めるための手段として「退職代行サービス」が選ばれるケースが増加しています。
(5)退職しにくい企業文化
近年は売り手市場が続き、企業の人材不足が深刻化しています。
とくに中小企業では、少人数で業務を回す職場が多く、社員一人ひとりがキャパシティぎりぎり、あるいはそれ以上の負担を抱えているのが実情です。
こうした環境では、「自分が辞めたら他の人に迷惑がかかる」と感じて、退職を切り出せないケースも少なくありません。
その結果、どうしても自分では言い出せない人が「退職代行サービス」に頼るケースが多いです。
さらに、従来の退職手続きでは申し出から実際の退職日までに出勤を続ける必要があります。
人手不足の職場で「気まずい空気の中、残りの勤務をこなす」ことにストレスを感じる人も多く、即日で辞められる退職代行サービスが選ばれる理由になっています。
(6)依然残るパワハラやブラック企業の存在
労働環境が改善されたとはいえ、パワハラをする人やブラック企業は、依然として存在しています。
昭和や平成の時代では、大声での叱責や多少のパワハラ的な言動は当たり前であり、新人はそれに耐えるのが普通のこととされていました。
この時代に働いていた人が上司となっている企業では、悪気がなくとも高圧的に新人に接したり、上から目線でものを言ってしまいがちです。
Z世代はSNSでパワハラやブラック企業の実態を見聞きしているので、このような人が一人でもいれば「ブラック企業かも!身を守らなければ!」と感じるでしょう。
その結果として、彼らにとって怖い上司と話さずに済む退職代行を利用して辞めていきます。
3.なぜ退職代行を利用するのか?若者の心理

ここまで退職代行利用者が増えた背景について説明しました。
次は、退職代行を利用する若者の心理を知っていきましょう。
- 引き止められたくない
- 会社を休みがちになっており出勤しづらい
- 退職させてもらえない可能性がある
- 直接の対話を極力避けたい
- 辞め方がわからないのでプロに任せたい
(1)引き止められたくない
退職代行を利用する若者は「引き止められたくない」と思っています。
Z世代は相手に嫌われたくないという傾向が強いので、相手に嫌われない回答を本心とは裏腹に発してしまう可能性が高いからです。
つまり、強く引き止められれば上司に嫌われたくないあまりに「じゃあ続けてみます」と答えてしまう可能性があるということです。
自分のこのような心理を理解しているからこそ、直接対話しなくて良い退職代行を利用し、穏便かつ引き止められずに辞めたいと感じています。
(2)会社を休みがちになっており出勤しづらい
退職代行利用者のなかには、すでに会社を休みがちになっている人が多いです。
「退職する」というだけのために出勤するのが気まずく、出社せずに退職できる退職代行を選んでいます。
例えば、入社後すぐにストレスで体調を崩し、月の半分程度しか出勤できていない社員がいたとしましょう。
この人が改めて出勤し、上司に面談で退職を申し出るのは心理的なハードルが高いです。
一方で退職代行を利用すれば、そのまま出社せずに退職の手続きが進みます。
「会社を休んだままフェードアウトするように辞めたい」という心理から、退職代行の利用者が増えているのです。
(3)退職させてもらえない可能性がある
若者は「辞めたいと言っても、辞めさせてもらえない」と考えて、安全策として退職代行を利用しています。
もちろん退職は社員の権利ですが会社によっては、直属の上司にとっては管理不足と評価されることもあります。
そのため、なかには無理に引き止めたり、高圧的に退社を認めないような会社もあるためです。
例えば、人手不足でほかの社員が退職させてもらえなかった事実を目の当たりにしたような場合、若手は当然「自分も辞めさせてもらえないかも」と考えます。
自ら交渉しても退職させてもらえない可能性があるので、プロである退職代行サービスを利用して、確実に退職したいと考えています。
(4)直接の対話を極力避けたい
Z世代は「人との衝突を避けたい」という心理傾向が強く、直接上司と話し合うのを避けたいと考えています。
そのため、上司に直接「辞めたい」ということができません。
辞めたい自分と引き止めたい上司で意見が対立して「怒られたらどうしよう」「嫌なことを言われたらメンタルが」と考えて、退職の際に直接話すのを避けます。
その点退職代行は第三者が間に入るため対話の必要はありません。
このような心理を抱えるZ世代にとって、退職時の最適な選択肢になっています。
(5)辞め方がわからないのでプロに任せたい
若者はこれまで会社を辞めた経験がないため、「失敗を避けるためにも退職のプロに任せたい」と考えています
これは、Z世代に多い「わからないことはやりたくない、わかる人にやってもらいたい」という価値観からです。
インターネット検索ですぐに最適解を探せる時代に育った彼らは、わからないことをやるのに強い心理的抵抗があります。
そのため、ノウハウを知らない「退職」に対して不安を感じ、プロである退職代行を利用して安全に退職したいと考えています。
4.若者の退職代行利用を防ぐには?企業がとるべき対策

若者により長く働いてもらうために、企業がとるべき対策を紹介します。
「今の若者は」と否定するのではなく、価値観をブラッシュアップし、若者と一緒に働ける環境づくりに取り組んでみましょう。
- 若者の価値観を先入観で否定しない
- 採用段階で会社の価値観を伝える仕組みを作る
- 辞める前に相談できる環境を作る
- 社員が「ずっと働きたい」職場作り
(1)若者の価値観を先入観で否定しない
退職代行サービスを利用したり、入社後すぐに退社する若者に対して「最近の若いやつは」と言いたくなる気持ちは理解できます。
しかし、今すべきは若者の価値観の否定ではなく、その価値観が生まれた背景です。
Z世代はコロナ禍や不況などの不安定な時代を生きてきた世代であり、価値観がほかの世代と違うのは当たり前といえます。
まずは価値観に寄り添って「そういう考え方があるんだ」と受け止めたうえで、変えられる部分は変えていきましょう。
たとえば、今の若者はSNSを通じて「一度失敗したら終わり」という事例を何度も目にしており、それにより極度に失敗を恐れます。
この価値観に寄り添って行動すれば、ミスをした社員がすぐに心折れて退社するような事例は防げるはずです。
たとえば、失敗した際に社員を責めず一緒に解決策を考え「失敗しても、リカバリーできる」ことを教えてあげれば、すぐに退社を選ぶことはなくなるでしょう。
このようにZ世代の価値観を理解したうえで接し方を少し変えることで、若者が退職代行の利用を選ぶ頻度は減らせるはずです。
(2)採用段階で会社の価値観を伝える仕組みを作る
入社してすぐに退職代行を利用する若者の多くは、入社前に聞いていた説明と入社後の現状が違うことに不満を抱いています。
いわゆる入社後ギャップが大きいほど、退社を選びやすくなります。
そのため、採用段階で会社の価値観を伝える仕組み作りが重要です。
従来のように会社のメリットを打ち出すだけでは、今の時代に即していません。
若者に対して一歩踏み込んだ、見る人によっては会社にデメリットの印象を与えてしまうことがあるかもしれない会社の価値観を伝えることで入社後ギャップを抑え、社風や風土に理解がある若者を採用できます。
たとえば、TikTokの@kawasaki_kouichiは、SNSを通じて「我が社は昭和の価値観がある社風だ」ということをアピールしています。
@kawasaki_kouichi 会社の飲み会参加してますか? #オーダースーツ #スーツ #川崎浩一 ♬ オリジナル楽曲 – K-51川崎浩一@オーダースーツ社長@アパレル社長
「飲み会に残業代がつかないのは当たり前だ」とはっきり社長が伝える(もちろんなぜつかないか?の理由や考えも添えることが大切)ことで、応募者に対して無駄な理想を抱かせず、納得した人材だけを採用できている好例といえるでしょう。
いわばSNSが応募者のスクリーニング的な機能を果たしているわけです。
このように採用LPやSNSを通じて、自社が大切にしている価値観を発信してみてください。
若者が気になる「飲み会は多いのか(強制か?)・休日に社員の集まりに参加しないといけないのか」など、リアルな情報を伝えましょう。
SNSで発信する際に社員の顔出しが難しい場合は、アニメ動画を使うのもおすすめです。
アニメーションで「とある社員の1日」を再現したり、休日の集まりの様子を再現して後悔するのも良いでしょう。
採用戦略を立てる際に、従来よりも会社のリアルが伝わる方法を検討してみてください。
入社後ギャップを抑える方法については、こちらの記事をご覧ください。
(3)辞める前に相談できる環境を作る
「退職代行を利用する前に一言相談してくれたら…」と思う人もいるでしょう。
しかし、若者の多くが職場に相談できる人がいない、または相談する窓口がわからないと思っています。
つまり、若者にとって相談しにくい環境を作っている可能性があるということです。
これを解決するためには、匿名で相談できるチャットを設けたり、第三者を入れたキャリア面談を開催したり、月に1度雑談できる集まりを作るのも良いでしょう。
退職代行を利用する前に「誰かに話せる環境」があれば、辞めたいという気持ちを打ち明けてくれるかもしれません。
または、新入社員一人ひとりに対してメンターがつく制度を取り入れるのも良いでしょう。
辞めたい理由を直接聞くことができれば、事前に退職を食い止めることもできます。
(4)社員が「ずっと働きたい」職場作り
若手社員の定着率を上げるためにも、社員が働きたくなる環境作りにも力を入れましょう。
採用と同時進行で職場環境を変えていくことで、社員が「辞めたい」と思う機会自体を減らすことができます。
たとえば、以下のような仕組み作りをすることで若者の「辞めたい」を防げます。
| 若者の不満 | 企業にできる改善 |
|---|---|
| マニュアルがなく曖昧な仕事の指示 | 仕事内容のマニュアル化指示の明文化 |
| 部署異動で理想の仕事ができなくなる | 異動前に明確に仕事内容を伝えて合意形成する |
| 自分の将来性が見えない | 明確なキャリアパスや昇進基準の提示 |
| 頑張っても評価されない、感謝されない | 感謝と承認の社内風土作り(頭ごなしに否定せず、認めてから教えたり、諭したりする) |
若者の要望をすべて飲む必要はありませんが、これらはZ世代に限らず、全世代が会社へ抱く不満と共通するはずです。
日本企業にありがちな「なんとなく昔からこうだから」という仕事の仕方や、「会社のいうことを聞くのが当たり前」という風潮を脱することが、社員全体の幸福度を上げて、定着率を上げることにつながるでしょう。
退職代行利用に備えて企業がとるべき対策は、こちらの記事でも紹介しています。
まとめ
退職代行サービスの利用増加は時代の流れであり、企業はZ世代の価値観を理解した採用・定着戦略を考える必要があります。
大切なのは会社の「良いところ」だけではなく「会社の大切にしている価値観」を伝えることで入社後のギャップを減らし、若者が「ずっと働きたい」と思える職場づくりです。
「採用革命®」が提供するアニメーション動画は、記憶定着率が人のプレゼンより約22%高く、Z世代に企業の魅力やリアルを効果的に伝えるツールとして注目されています。
情報を「短く」「印象に残る」形で伝え、若者との接点を創出できる採用革命のサービスは、現代の採用課題に対する効果的な解決策といえるでしょう。
また「採用革命®️」では、採用LP強化やSNSの運用代行も可能です。
退職代行利用者の増加にお悩みなら、ぜひ一度ご相談ください。
Z世代の採用につながるアニメーション動画の制作・運用なら「採用革命アニメーション®」
採用革命アニメーションは、今年で創業65年目の広告会社である株式会社JITSUGYOが運営する採用に特化したアニメーション動画制作サービスです。
アニメーション制作は参入障壁が低く、社歴が短い会社やシェアオフィスで運営している会社が多いのが現状です。そんな中でも、弊社は2023年で66期目になり一般企業だけでなく、国や地方自治体、大学、著名人といったお客様との取引も多数ございます。
65年以上続く広告会社であり伝えることのプロだからこそ、誇れる実績が多数ございます。65年以上続く広告会社だからこそできる圧倒的なシナリオ作成力で、営業から取材、制作、広告運用まで一気通貫したサービスをご提供いたします。
アニメーションは作って終わりではなく、その後の採用に対して、認知拡大やマーケティング部分までサポートできるのが弊社の魅力です。Google広告公式認定資格保持者も社内に在籍していますので、専門的でより効果的な施策を実施することが可能です。
採用につながるアニメーション制作をご検討中の企業担当者様は、株式会社JITSUGYOが運営する採用革命アニメーション®に、ぜひ一度ご相談ください。
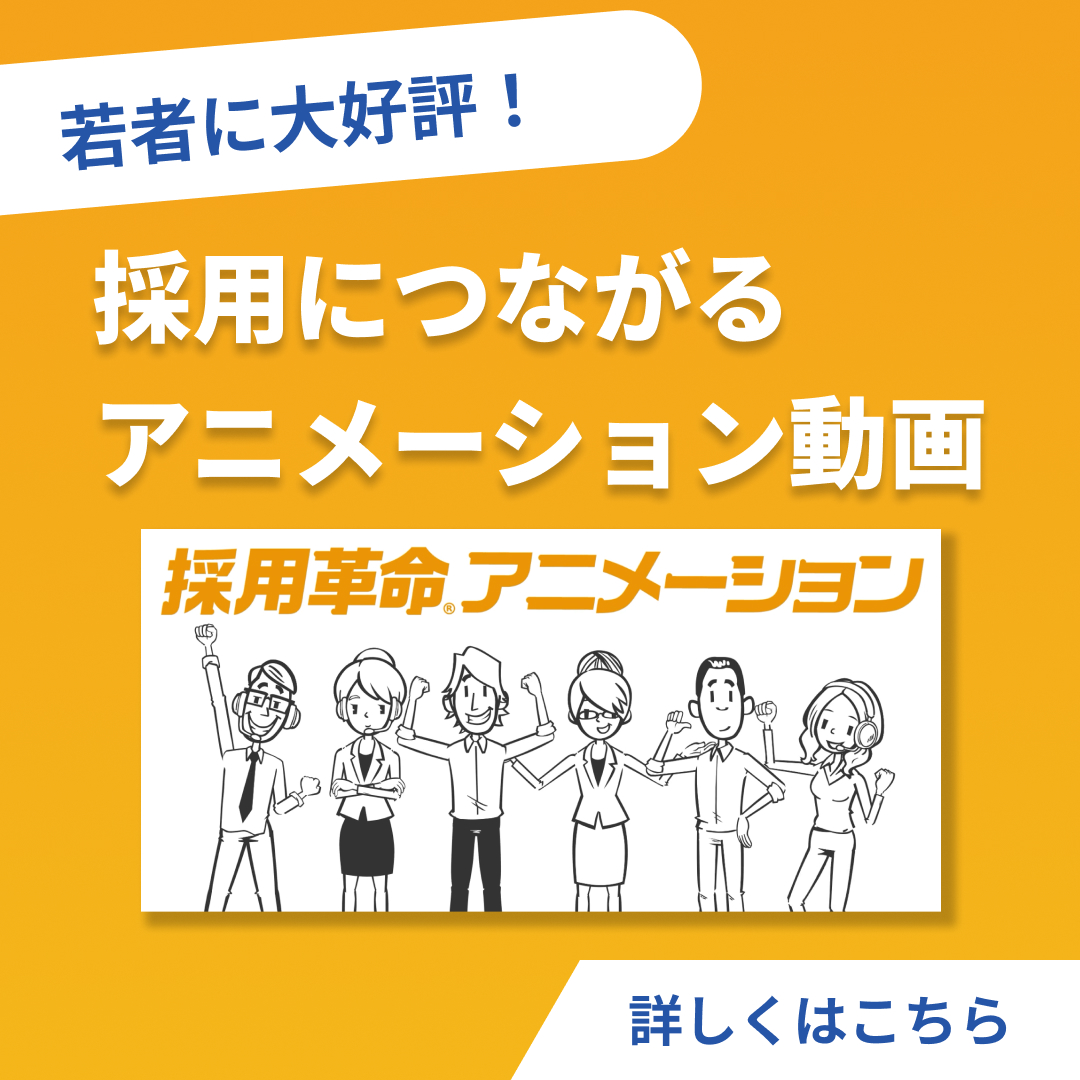

採用革命®アニメーション編集部
年間400本以上の動画制作実績を誇る採用革命®アニメーションの編集メンバー。動画を使ったマーケティングについて、老舗広告会社の視点から解説します。



