
「若者を飲み会に誘っても、嫌な顔をされるんだろうなあ…」
「コミュニケーション不足で離職するのに、飲み会を拒否するのはなぜ?」
実はZ世代は、飲み会が嫌いなわけではないことが分かっています。
ただ、昭和・平成初期世代と異なり、飲み会=コミュニケーションという認識はありません。
この記事では、月に1回の飲み会が離職率を下げた事例やZ世代の意外な本音、特にブルーワーク業界で飲み会が離職率を下げるのに有効である理由を紹介しています。
1.月1回の飲みニケーションが離職率を下げる!?

飲みニケーションは「古い」と言われがちですが、実は『離職率を下げた』事例もあります。
そもそも若者は本当に飲み会を嫌っているのかを調べたところ、そこにはZ世代の意外な本音が隠されていました。
- 若者は飲み会を嫌っているわけではない
- 強制ではない飲み会が信頼関係を深める
- ブルーワーカー業界では飲み会が離職防止につながるというデータも
(1)若者は飲み会を嫌っているわけではない
Z世代は「飲み会そのもの」が嫌いなわけではありません。
多くの人が「若者は会社の飲み会を敬遠している」と考えがちですが、LinkedInの調査では「若者は飲み会自体を嫌っているわけではない」という結果も出ています。(参考:実は飲み会好き?? Z世代の意外な本音)
彼らが嫌がっているのは、頻繁な飲み会でプライベートが奪われることや、暗黙の了解として参加や幹事を求められる「強制感」です。
「若者は誘われたら必ず参加するもの」「飲み会も仕事のうちだから、私生活より優先して当然」という空気に、強い抵抗を感じているのです。
また、Z世代は「お酒を飲んで距離を縮める」という価値観にはあまり馴染みがありません。
職場でほとんど話したことがない相手と、いきなり飲み会で長時間一緒に過ごすことに気まずさを感じ、「そこまでして行く必要はない」と判断するケースも多いでしょう。
一方で、日頃から職場でのコミュニケーションが取れていて、信頼できる先輩や同僚であれば、食事やお酒の席に前向きに出かけている若者も少なくありません。
つまり、「意味のあるコミュニケーションができること」と「プライベートを侵食しすぎないこと」が満たされれば、Z世代も飲み会には参加したいと考えています。
たとえば、月に1回程度・2時間ほどでサクッと終わる飲み会であれば、「これなら参加してもいい」と感じてもらいやすくなるでしょう。
(2)強制ではない飲み会が信頼関係を深める
Z世代にとって大事なのは、「全員参加必須の飲み会」ではなく、「行きたい人が行けるフラットな場」です。
お酒が飲めない人でも楽しめるように、アルコール以外のドリンクが充実した店を選ぶことや、焼肉・寿司など純粋に食事が楽しめる場にすることがポイントになります。
また、長時間ダラダラ続けず、2時間程度で区切る、一次会で解散する、会社負担を大きくするなど、「時間もお金も取りすぎない配慮」があると、若手も参加しやすくなります。
その結果として、業務時間内では話しきれない本音や相談がしやすくなり、上司・同僚との信頼関係づくりにプラスに働くはずです。
(3)ブルーワーカー業界では飲み会が離職防止につながるというデータも
実際に、適度な頻度での飲み会が離職防止につながるというデータも出ています。
株式会社JITSUGYOがZ世代ブルーワーカーを対象に行った調査では、「働き続けたい職場」の1位が「月1回飲み会がある職場」だったと報告されています。
この結果は、「毎週のように強制参加の飲み会を開く」ことではなく、「月1回程度、気軽に参加できる飲み会」があることで、現場の雰囲気が良くなり、相談しやすさや安心感が高まることを示しています。
ブルーワーカー業界に限らず、適切な頻度とスタイルさえ守られれば、飲み会は若手の定着やエンゲージメント向上に役立つ施策になり得ると言えるでしょう。
2.特にブルーワーク業界で飲み会が重要な理由

ブルーワークの現場は、年齢差や上下関係がはっきりしており、業務中は安全管理や作業効率が優先されるため、落ち着いて対話する時間を取りにくい環境です。
だからこそ、仕事から一歩離れて本音で話せる飲み会が重要。
単なる「慰労の場」ではなく、Z世代を含む若手との関係づくりや、現場の空気を良くするための重要な機会になり得ます。
- 普段怖くて話せない上司ともフラットに話せる場になる
- 現場リーダーの育成にもつながる
- 日常では話せない悩み・改善提案の共有場になる
(1)普段怖くて話せない上司ともフラットに話せる場になる
現場では、安全管理や指示が中心になり、上司が怖い存在になりやすいものです。
しかし、仕事を離れた飲み会の場なら、1個人として関わりやすくなります。
このとき重要なのが、上司側のコミュニケーション力です。
会社が目指す方向性を自分の言葉で語り、部下の悩みを「自分事」として受け止めて傾聴する、こうした双方向のコミュニケーションがあってこそ、厳しいけれど信頼できる上司として若手に伝わります。
(2)現場リーダーの育成にもつながる
飲み会は、次世代リーダーの練習の場としても機能します。
幹事や席順の調整、会話のきっかけづくりなどを若手に任せることで、段取り力や気配り、場を回す力が自然と鍛えられます。
また、上司があえて若手に話を振ったり、意見を求めたりすることで、「人前で話す」「先輩の前で自分の考えを伝える」経験値も積めるでしょう。
こうした経験が、現場で指示を出したりチームをまとめたりする力につながっていきます。
(3)日常では話せない悩み・改善提案の共有場になる
ブルーワークの現場は常に時間に追われており、「ちょっといいですか」と切り出しにくい雰囲気になりがちです。
その結果、小さな不満や不安、改善アイデアが埋もれてしまいます。
強制ではない飲み会があると、「実はシフトがきつい」「この道具が使いづらい」「ここが危ないと感じている」といった本音が出やすくなります。
管理側にとっても、早期離職のサインや現場改善のヒントをつかむ貴重な機会です。
現場の声がきちんと聞かれ、改善につながる実感を持てれば、若手の納得感や職場への信頼も高まりやすくなります。
3.働き続けたい職場を作るには「コミュニケーション」が欠かせない

Z世代に限らず長く働きたいと思えるかどうかは、待遇だけでなく「この人たちと一緒に働きたい」と感じられるかどうかに大きく左右されます。
その土台になるのが、日頃からのコミュニケーションです。
具体的にどのようなコミュニケーションが必要なのか、詳しく解説します。
- 若者が望むのは「生産性の高い」コミュニケーション
- 飲み会だけでなく社内での会話も重要
(1)若者が望むのは「生産性の高い」コミュニケーション
Z世代は、時間対効果や効率を重視する傾向が強い世代です。
そのため、ただお酒を飲んで酔うだけ、上司に気を遣って終わるような飲み会には価値を感じません。
一方で、仕事に役立つ話が聞けたり、自分の悩みやキャリアについて相談できたり、お互いの考え方を深く理解できる場であれば、前向きに参加したいと考えています。
「行ってよかった」「明日からの仕事に生きる」と感じられる、生産性の高いコミュニケーションを用意できるかどうかがポイントです。
(2)飲み会だけでなく社内での会話も重要
若手が「この職場で働き続けたい」と思うには、飲み会だけに頼らず、日常のコミュニケーションを整えることも欠かせません。
休憩時間のちょっとした雑談や、始業前後の声かけなど、業務外の会話が安心感や信頼感を育てます。
また、入社後のギャップを減らすには、入社前からの相互理解も重要です。
選考や面談の段階で、仕事の実態や職場の雰囲気、期待する役割を丁寧に伝え、候補者側の価値観や希望もきちんと聞く、この事前のコミュニケーションを重ねておくことで、「思っていた職場と違った」という早期離職のリスクを減らすことができます。
4.離職率を下げるにはギャップを生まない「伝え方」が重要

離職率を下げるうえで重要なのは、待遇だけでなく「入社前に聞いていた話と、実際に働いてみた現場とのギャップ」を小さくすることです。
そのためには、採用段階から会社の雰囲気や仕事のリアルを、できるだけ正確に・わかりやすく伝える工夫が欠かせません。
- 早期離職の原因は入社前と後のギャップ
- 会社の雰囲気や実情を事前に伝えるのが大切
- アニメーション動画ならリアル×親しみやすさを両立できる
(1)早期離職の原因は入社前と後のギャップ
早期離職の理由としてよく挙がるのが、「聞いていた話と違う」「想像よりずっときつかった」といった入社前後のギャップです。
仕事内容・勤務時間・人間関係・職場の雰囲気など、候補者がイメージしていた職場像と、実際の現場に差があるほど、「ここで長く働くのは難しい」と感じやすくなります。
つまり、ギャップを減らすことが、そのまま早期離職のリスクを下げることにつながります。
(2)会社の雰囲気や実情を事前に伝えるのが大切
ギャップを防ぐには、良い面だけをアピールするのではなく、現場の実情も含めて事前に伝える姿勢が重要です。
具体的には、次のような情報をできるだけわかりやすく共有しておくと効果的です。
- 1日の仕事の流れや、繁忙期の忙しさ
- チーム構成や年齢層、現場の雰囲気
- 大変な点と、それをどう乗り越えているか
- 成長実感やキャリアパスの具体例
こうした情報を正直に伝えることで、「思っていたよりきつい」「こんなはずじゃなかった」というギャップを減らし、「それでもここで働きたい」と納得して入社してもらいやすくなります。
(3)アニメーション動画ならリアル×親しみやすさを両立できる
とはいえ、紙の求人票やテキストだけで現場の空気感を伝えるのには限界があります。
そこで有効なのが、アニメーション動画を使った情報発信です。
アニメーション動画には、次のようなメリットがあります。
- アニメ表現はZ世代との親和性が高く、抵抗感なく見てもらいやすい
短い尺の中に情報を凝縮でき、タイパを重視する若者にもマッチする - ストーリー仕立てにすることで、仕事の流れや現場の雰囲気をイメージしやすくなる
- 実写だと「きつさ」や「汚れ」の印象が前面に出やすいブルーワーク職でも、アニメなら魅力をソフトに伝えられる
このように、アニメーション動画を活用すれば、仕事のリアルさと応募者への配慮を両立しながら、入社前のギャップを小さくしていくことができます。
5.「採用革命®️」のアニメーションでリアルを伝えよう

入社前後のギャップを減らし、離職率を下げたい企業にとって、採用向けアニメーションは有効な手段の一つです。
なかでも、採用コミュニケーションに特化したアニメーションサービス「採用革命」を活用すれば、Z世代にも伝わりやすい形で、自社のリアルな姿を届けやすくなります。
採用革命ではアニメーションの制作はもちろん、それに伴う採用LPの改善や採用活動全般のサポートも可能です。
各分野に精通したスタッフが在籍しているので、ブルーワーク業界だけでなく幅広い業界で、自社のリアルが伝わるようにシナリオを詳細に設計、アニメーションを作成します。
まとめ
Z世代は、決して「飲み会そのもの」が嫌いなわけではありません。
嫌っているのは、頻繁な開催でプライベートが奪われることや、暗黙の強制・上下関係だけが強調される場です。
事実ブルーワーク業界では、適切に設計された飲み会が、上司との信頼関係づくりや現場リーダーの育成、本音の悩み・改善提案を引き出すうえで大きな役割を果たします。
若者が求めているのは「ただ酔う場」ではなく、仕事にも自分の将来にもプラスになる、生産性の高いコミュニケーションです。
もうすぐ忘年会シーズン、早速Z世代と生産的なコミュニケーションができる飲み会を検討してみませんか?
Z世代の採用につながるアニメーション動画の制作・運用なら「採用革命アニメーション®」
採用革命アニメーションは、今年で創業65年目の広告会社である株式会社JITSUGYOが運営する採用に特化したアニメーション動画制作サービスです。
アニメーション制作は参入障壁が低く、社歴が短い会社やシェアオフィスで運営している会社が多いのが現状です。そんな中でも、弊社は2023年で66期目になり一般企業だけでなく、国や地方自治体、大学、著名人といったお客様との取引も多数ございます。
65年以上続く広告会社であり伝えることのプロだからこそ、誇れる実績が多数ございます。65年以上続く広告会社だからこそできる圧倒的なシナリオ作成力で、営業から取材、制作、広告運用まで一気通貫したサービスをご提供いたします。
アニメーションは作って終わりではなく、その後の採用に対して、認知拡大やマーケティング部分までサポートできるのが弊社の魅力です。Google広告公式認定資格保持者も社内に在籍していますので、専門的でより効果的な施策を実施することが可能です。
採用につながるアニメーション制作をご検討中の企業担当者様は、株式会社JITSUGYOが運営する採用革命アニメーション®に、ぜひ一度ご相談ください。
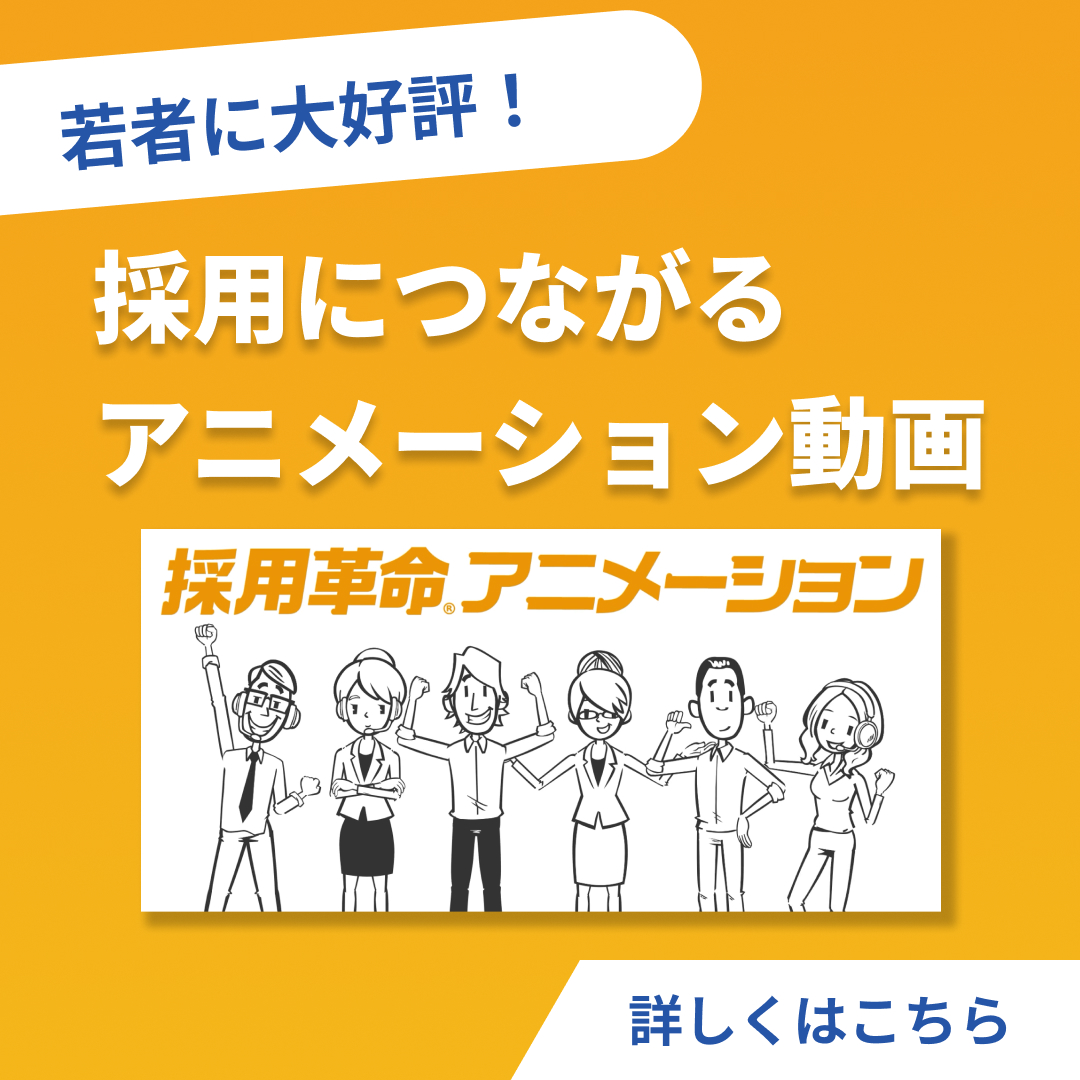

採用革命®アニメーション編集部
年間400本以上の動画制作実績を誇る採用革命®アニメーションの編集メンバー。動画を使ったマーケティングについて、老舗広告会社の視点から解説します。



