
「採用直結型インターンシップとはどんなもの?従来のものと比べてメリットは?」
「大手企業に比べて知名度がないから、優秀な学生の母集団形成ができない…」
このような悩みを抱える中小企業の採用担当者は多いのではないでしょうか。
実は、新卒採用市場は大きく変化しており、日本経済新聞によれば、大学3年生の内定率はすでに約5割(49.8%)に達し、内定者の54.2%が10社以上のインターンシップに参加しています。
この記事では、早期化する採用市場で中小企業が優秀な人材を確保するために効果的な「採用直結型インターンシップ」について解説します。
1.採用活動におけるインターンシップの現状

採用市場では、インターンシップが単なる職業体験ではなく、採用活動の中核となっています。
企業と学生の双方がインターンシップを重視し、その位置づけが大きく変わってきました。
- 新卒採用は早期化が進行
- 採用直結型インターンシップへ注目が集まる
(1)新卒採用は早期化が進行
新卒採用市場は急速に早期化が進んでおり、日本経済新聞によれば、2025年卒の大学3年生の内定率はすでに約5割(49.8%)に達しています。
さらに、内定者の54.2%が10社以上のインターンシップに参加しており、インターンシップの需要の高さも顕著です。
大手企業が早期のインターンシップで優秀な学生を確保する採用戦略を強化した結果、従来の採用スケジュールである2〜3月の合同企業説明会に参加する学生は年々減少傾向にあり、多くの企業から「例年に比べて参加者がかなり減った」という声も。
このような状況では、従来の採用手法に固執する企業、特に中小企業は、すでに多くの優秀な学生が内定を得た後の限られた人材からの採用を強いられることになります。
(2)採用直結型インターンシップへ注目が集まる
採用直結型インターンシップは、早期化する採用市場で注目を集めている新しいインターンの形です。
この採用手法は、インターンシップでの評価を本選考に直接活用できるのが特徴であり、実施期間など一定の条件を満たせば選考プロセスを短縮できる仕組みです。
学生側にとっては、複数企業の選考を効率よく進められる「効率的な就活」を実現する手段として人気があり、多くの学生が参加しています。
一方で企業側にとっても、早期に優秀な人材を確保できる可能性が高まるため、積極的に導入する企業が増加しています。
この状況を受けて、現在の採用市場では企業が限られた優秀な人材を取り合う厳しい競争が生まれており、中小企業が大手企業と競争して人材を確保するためには、この新しい採用トレンドへの対応が不可欠です。
2.採用直結型インターンシップとは?

採用直結型インターンシップは従来のインターンシップとは目的も仕組みも異なります。
まずは採用直結型インターンシップの概要を理解しておきましょう。
- 採用直結型インターンシップの概要
- 企業で開催するインターンシップの種類
- 採用直結型と通常のインターンシップの違い
(1)採用直結型インターンシップの概要
採用直結型インターンシップとは、インターンでの評価を本選考に活かし内定に直結させる仕組みです。
従来のインターンシップが「企業理解の促進」や「就業体験の提供」を主な目的としていたのに対し、採用直結型インターンシップは明確に「採用」を目的としています。
具体的には、学生がインターンシップで一定の成果を上げるか、実施期間や課題内容などの条件を満たした場合に、通常の選考プロセスを一部免除するなどの特典が与えられます。
これにより、インターンシップと採用プロセスが直接結びついた形式となり、企業と学生の双方にとって効率的な採用活動が可能です。
この仕組みは早期に優秀な人材を確保したい企業と、効率的に就職活動を進めたい学生のニーズがマッチする方法として、急速に採用市場で広まっています。
(2)企業で開催するインターンシップの種類
『令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります|厚生労働省』によると、インターンシップは以下4つのタイプに分類されることになりました。
| タイプ | 募集方法 | 内容・位置づけ | 実施期間 |
|---|---|---|---|
| オープンカンパニー | 多くの学生を対象に広く募集 | 企業説明会の延長線上として実施されることが多い | 1日~3日程度の短期間 |
| キャリア教育 | 多くの学生を対象に広く募集 | 企業説明会の延長線上として実施されることが多い | プログラムによる |
| クローズド型インターンシップ | 選考を経て参加者を絞り込む | 実際の業務に近い体験を提供 | 1週間~1ヶ月程度の中長期 |
| 採用直結型インターンシップ | 選考を行い、意欲・適性の高い学生を選抜 | 本選考の一部として位置づけ、評価が採用選考に直結 | 期間は様々(短期から長期まで) |
この改正により厳密にインターンシップと呼べるのは『最低5日以上実施され、就業体験ができる者のみ』と定義されています。
短期間のインターンシップは『オープンカンパニー』『キャリア教育』と区分され、あくまで情報の提供や教育を目的としたものと定義されます。
この中でも近年特に注目されているのが採用直結型インターンシップです。
企業と学生の双方にとって効率的な採用活動を実現できるため、導入する企業が増加しています。
(3)採用直結型と通常のインターンシップの違い
採用直結型インターンシップと通常のインターンシップの主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 採用直結型インターンシップ | 通常のインターンシップ |
|---|---|---|
| 主な目的 | 採用活動の一環 | 企業理解・業界理解の促進 |
| 選考との関係 | 評価が本選考に直結 | 選考とは別のプロセス |
| 学生のメリット | 選考の一部免除・早期内定の可能性 | 業界・企業研究、スキル向上 |
| 企業のメリット | 早期人材確保、ミスマッチ防止 | 企業ブランディング、人材発掘 |
| 実施時期の傾向 | 3年生夏~秋が多い | 3年生春~夏が多い |
最も大きな違いは選考に直結する要素があるかどうか、また企業側の目的です。
3.なぜ中小企業こそ採用直結型インターンシップが重要なのか

中小企業こそ採用直結型インターンシップを活用すべき理由があります。
その理由を詳しく説明します。
- 大手の採用手法の変化に対応する必要がある
- 合同説明会に頼るだけではニーズに適う人材採用が難しい
(1)大手の採用手法の変化に対応する必要がある
中小企業は大手企業の採用戦略の変化に対応し、優秀な人材を確保するように戦略を立てなければなりません。
大手企業の採用戦略を意識せずにいると、限られた人材しか自社で採用できない可能性があるためです。
まず現状では大手が早期からインターンシップを活用し、採用活動を開始しています。
その結果優秀な学生は早期に内定を獲得しており、そもそも合同企業説明会へ参加しないパターンも増えています。
このような状況下で、中小企業が従来の採用スケジュールに固執していては、優秀な学生を獲得できません。
この変化に対応するためには、中小企業も採用直結型インターンシップを導入し、早期から学生にアプローチする必要があります。
大手企業の動向に合わせて採用戦略を調整することで、限られたリソースの中でも効果的な採用活動を展開することが可能になります。
(2)合同説明会に頼るだけではニーズに適う人材採用が難しい
大手の採用戦略の変化により、従来の合同説明会だけでは、質の高い人材の確保が困難になっています。
2〜3月の合同説明会に参加する学生は年々減少しており、「例年に比べて参加者がかなり減った」という声が多くの企業から聞かれています。
さらに、業界内では「集団合説に来る学生は情弱者が多い」という厳しい意見も。
もちろん、その中にも優秀な人材はいますが、質・量ともに企業のニーズを満たす人材を確保できないリスクは高まっているといえるでしょう。
この状況に対応するためには採用直結型インターンシップを実施し、早期から自社に興味を持つ学生にアプローチする必要があります。
インターンシップを通じて実際の業務を体験してもらうことで、学生と企業の相互理解が深まり、自社のニーズに合った人材を確保できる可能性が高まります。
4.採用直結型インターンシップのメリット

採用直結型インターンシップには、中小企業にとって特に重要ないくつかのメリットがあります。
- 選考の手間を削減し優秀な学生を採用できる
- 仕事を疑似体験させ学生の内定辞退を防止できる
- 学生のミスマッチを防ぎ定着率を高める
- 採用コストを削減できる
(1)選考の手間を削減し優秀な学生を採用できる
採用直結型インターンシップには、選考を効率化し、優秀な学生を採用できるというメリットがあります。
インターンシップ中の学生の働きぶりや能力、人柄などを直接評価し、その評価をそのまま本選考に活かせるからです。
これにより、選考プロセスの一部または全部を省略でき、さらには働きぶりの良い学生に内定を出すことができます。
具体的には、インターンシップで高い評価を得た学生に対して、筆記試験の免除や面接回数の削減など、選考プロセスを短縮することが可能です。
場合によっては、インターンシップの成績が特に優秀であれば、その場で内々定を出すことも可能です。
このような仕組みは、採用担当者の負担を軽減しながら、早期に優秀な学生を確保することを可能にします。
(2)仕事を疑似体験させ学生の内定辞退を防止できる
採用直結型インターンシップの活用により、内定辞退を大幅に減らす効果があります。
インターンシップを通じて実際の業務を体験させることで、学生は入社後の仕事や職場環境について理解したうえで、内定を獲得することにつながるからです。
これにより「思っていた仕事と違った」という理由での内定辞退を防止する効果があります。
インターンシップを通じて企業の実態や魅力を直接伝えることで、学生の企業理解を深め、入社への意欲を高めることができます。
また、インターンシップ期間中に学生と社員が交流する機会を設けることで、職場の雰囲気や人間関係についても理解を深めてもらうことも可能です。
(3)学生のミスマッチを防ぎ定着率を高める
採用直結型インターンシップは、入社後の定着率向上に大きく貢献する点もメリットです。
学生はどんな人と一緒に働くのか事前にわかり、また価値観が同じ人と働くやりがいを見つけたり、自身が将来どんな仕事をしたいかを見つけるヒントにもなります。
さらに、企業側も学生の能力や人柄、職場への適応性を見極められるのがメリットです。
このような相互理解に基づいた採用は、入社後のミスマッチを大幅に減らすことができ、結果として早期離職率の低減につながります。
また、入社後の教育コストの削減や、職場の安定性向上など、さまざまな二次的なメリットも期待できるでしょう。
(4)採用コストを削減できる
採用直結型インターンシップはトータルの採用コスト削減につながります。
選考プロセスの一部を省略できるため、面接官の人件費や会場費、選考にかかる時間的コストなどを削減可能です。
また、内定辞退率や早期離職率の低減にもつながるため、採用のやり直しによる追加コストの発生を防ぐ効果もあります。
中小企業にとって特に重要なのは、限られた採用予算の中で効率的に人材を確保できる点です。
大手企業のように大規模な合同説明会への出展や高額な就職情報サイトへの掲載に多くの予算を割くことが難しい中小企業でも、インターンシップという形で自社の魅力を直接伝える機会を設けることができます。
5.採用直結型インターンシップのデメリット

採用直結型インターンシップにはメリットだけでなく、いくつかの課題も存在します。
事前にデメリットについて理解を深め、適切な対策を考えておくことで、採用直結型インターンシップの成功確率を高めましょう。
- 長期のインターンシップで人的コストがかかる
- 学生の本気度を測りにくい
- 就職サイトへ掲載できない場合がある
(1)長期のインターンシップで人的コストがかかる
採用直結型インターンシップの実施には、社内リソースの確保が必須となります。
質の高い採用直結型インターンシップを実施するためには、プログラム設計や学生の指導・評価など、相当の社内リソースを投入する必要があるからです。
特に長期間のインターンシップでは、学生を受け入れる部署の社員が通常業務に加えて指導や評価も行わなければならず、その負担は小さくありません。
中小企業では人員に余裕がないことが多く、この人的コストが負担となるリスクがあります。
対策としては短期インターンと長期インターンを組み合わせ、人的コストを抑える方法があります。
まず広く学生を集めた1〜3日程度のオープンカンパニーで学生を選抜し、本格的な長期インターンへ招待する方法がおすすめです。
このように段階的な選考を行うことで、長期インターンの参加者を厳選でき、受け入れ部署の負担を必要最小限に抑えることができます。
また、短期インターンでは企業説明や簡単なワークショップなど、負担の少ないプログラムを実施し、長期インターンでより深い業務体験を提供するなどプログラムを変えることで、より人的負担を減らせるでしょう。
(2)学生の本気度を測りにくい
インターンシップに参加したからといって、就職意欲が高いとは限りません。
就活情報サイトなどを通じて広く募集すると、単に企業研究や業界研究のため、あるいは就活のスキルアップや体験目的で参加する学生も多く集まるからです。
また、インターンシップへの参加が本選考の一部を免除されるという「特典」だけを目的として応募してくる学生もいるため、単に選考を通過する能力が高いだけで、入社意欲が低い学生を採用してしまうリスクもあります。
本気度の高い学生のみをインターンシップに招待するためには、事前に明確な参加条件をつけるのが有効です。
例えば、エントリーシートに志望動機や将来のキャリアプランなどを詳細に記入してもらい、事前面談も実施することで、意欲の高い学生を選別できます。
また、インターンシップの募集要項に、このプログラムが採用直結型であることを明示し、就職意欲の高い学生をターゲットにすることも重要です。
(3)就職サイトへ掲載できない場合がある
採用直結型インターンシップを実施する場合、就職サイトへの情報発信の制約がある場合があります。
採用直結型インターンシップは、一部の就職情報サイトでは掲載基準に合わないとされる場合があるからです。
これは主に「学生の就業体験」という本来のインターンシップの趣旨から外れているとみなされてしまうからです。
このような制約により、大手就職情報サイトを通じた学生へのリーチが限定される可能性があり、特に知名度の低い中小企業にとっては大きな課題となります。
中小企業にできる対策としては、採用専用のオウンドメディアやSNSなど、複数の情報発信源をもつ方法が有効です。
また、大学のキャリアセンターと連携し、インターンシップの情報を直接学生に届けるルートを確保しましょう。
就職情報サイトに依存しない多様な情報発信チャネルを構築することで、より広く学生にアプローチすることが可能になります。
6.採用直結型インターンシップを成功させるためのポイント

採用直結型インターンシップを成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
特に中小企業が限られたリソースの中で効果的にインターンシップを実施するためのポイントを紹介します。
- 採用LPの強化など独自の採用戦略を立てる
- 自社の魅力や働き方を動画で伝える
- インターン実施後のフォローを徹底する
(1)採用LPの強化など独自の採用戦略を立てる
採用直結型インターンシップを成功させるには、採用LPの許可など独自の採用戦略が必要です。
従来の就職情報サイトへの依存型の戦略ではなく、ランディングページ(LP)やオウンドメディア、SNSでの情報発信に力を入れましょう。
例えば、採用LPで過去のインターン生の体験談や成長ストーリーを掲載したり、社員のインタビューの掲載で企業文化や働き方をリアルに伝えることができます。
また、明確な選考フローや評価基準の提示で応募ハードルを下げ、学生の不安を払拭する情報も重要です。
学生が欲しい情報を得られる環境を整えることで、採用直結型インターンに意欲のある学生が応募してくれる下準備ができます。
(2)自社の魅力や働き方を動画で伝える
現在の採用市場では、従来のテキスト資料ではなく、視覚的なコンテンツで自社の魅力や働き方を伝える方法がトレンドです。
特にアニメーション動画は多くの企業で活用されています。
これは、Z世代をはじめとした若い世代は幼い頃から動画コンテンツに親しんでおり、中でもアニメーション動画は記憶定着率が高く、短時間で多くの情報を得られると人気だからです。
例えば、社内の雰囲気や実際の実務の雰囲気を紹介する動画コンテンツ、社員の1日のルーティンをアニメ化したような動画もトレンドとなっています。
動画コンテンツは一度制作すれば繰り返し活用できるため、長期的に見れば採用コストの削減にもつながる投資といえるでしょう。
(3)インターン実施後のフォローを徹底する
採用直結型インターンシップ成功のコツは、インターン実施後のフォローを徹底することです。
インターンシップ終了後も関係性を維持する仕組みを作ることで、内定承諾率を高めることができます。
例えば、定期的な情報提供(メールマガジンやニュースレター)を通じて、企業の最新情報や業界動向を伝えることで、学生との接点を維持します。
さらにOB・OG訪問の機会提供や社員との交流イベントを開催することで、より深い企業理解を促進し、入社への意欲を高める工夫も重要です。
また個別のキャリア相談の機会を設けることで、学生の不安や疑問に丁寧に対応し、信頼関係を構築するのも良いでしょう。
SNSやLINEグループなどでのコミュニティを維持することで、気軽なコミュニケーションを継続し、学生が質問しやすい環境を整えるなど、今の若者に合わせたフォロー体制を構築することで、内定承諾率を高められます。
7.中小企業が採用競争で勝つには「採用直結型×オウンドメディア活用」がカギ

中小企業の採用成功には、採用直結型インターンシップとオウンドメディアの連携が重要です。
採用直結型インターンシップは早期に優秀な学生を確保し、ミスマッチを防止する仕組みとして機能します。
一方、オウンドメディアは自社の魅力やビジョンを継続的に発信し、学生の認知度と興味を高める手段となります。
この2つを効果的に組み合わせることで、知名度やリソースで大企業に劣る中小企業でも、自社に合った優秀な人材を確保することが可能になります。
具体的なオウンドメディアの活用方法としては以下のようなものを検討してみましょう。
- 採用特化型ブログ:業界の最新動向や自社の取り組み、社員の声などを定期的に発信
- SNSアカウント:Instagram、Twitter、YouTubeなどで日常の社内風景や社員の声を発信
- Wantedlyなどのプラットフォーム:自社のビジョンや社風を魅力的に発信
- 採用アニメーション動画:Z世代に刺さる動画コンテンツで企業の魅力を伝える
中小企業は大手企業に比べて知名度で劣りますが、オウンドメディアを活用することで自社の魅力を直接学生に伝えることが可能です。
また、採用直結型インターンシップの情報を自社メディアで発信することで、就職情報サイトの掲載制限という課題も克服できます。
特に、Z世代の記憶定着率が高いアニメーション動画を活用することで、企業のメッセージをより効果的に伝えられるでしょう。
まとめ
採用直結型インターンシップは、早期化する採用市場で中小企業が優秀な人材を確保するための重要な戦略です。
大学3年生の内定率が約5割に達し、従来の採用スケジュールが崩れる中、中小企業は新たな採用戦略の構築が求められています。
採用直結型インターンシップを実施することで、選考プロセスの効率化、内定辞退防止、ミスマッチ防止、採用コスト削減などのメリットが得られます。
もちろん、人的コストの増加や学生の本気度測定の難しさなどの課題もありますが、適切な対策を講じることでこれらの課題は克服可能です。
記事で紹介した採用直結型インターンシップのメリット、デメリットの双方を理解したうえで、自社の採用戦略を練り直してみてください。
Z世代の採用につながるアニメーション動画の制作・運用なら「採用革命アニメーション®」
採用革命アニメーションは、今年で創業65年目の広告会社である株式会社JITSUGYOが運営する採用に特化したアニメーション動画制作サービスです。
アニメーション制作は参入障壁が低く、社歴が短い会社やシェアオフィスで運営している会社が多いのが現状です。そんな中でも、弊社は2023年で66期目になり一般企業だけでなく、国や地方自治体、大学、著名人といったお客様との取引も多数ございます。
65年以上続く広告会社であり伝えることのプロだからこそ、誇れる実績が多数ございます。65年以上続く広告会社だからこそできる圧倒的なシナリオ作成力で、営業から取材、制作、広告運用まで一気通貫したサービスをご提供いたします。
アニメーションは作って終わりではなく、その後の採用に対して、認知拡大やマーケティング部分までサポートできるのが弊社の魅力です。Google広告公式認定資格保持者も社内に在籍していますので、専門的でより効果的な施策を実施することが可能です。
採用につながるアニメーション制作をご検討中の企業担当者様は、株式会社JITSUGYOが運営する採用革命アニメーション®に、ぜひ一度ご相談ください。
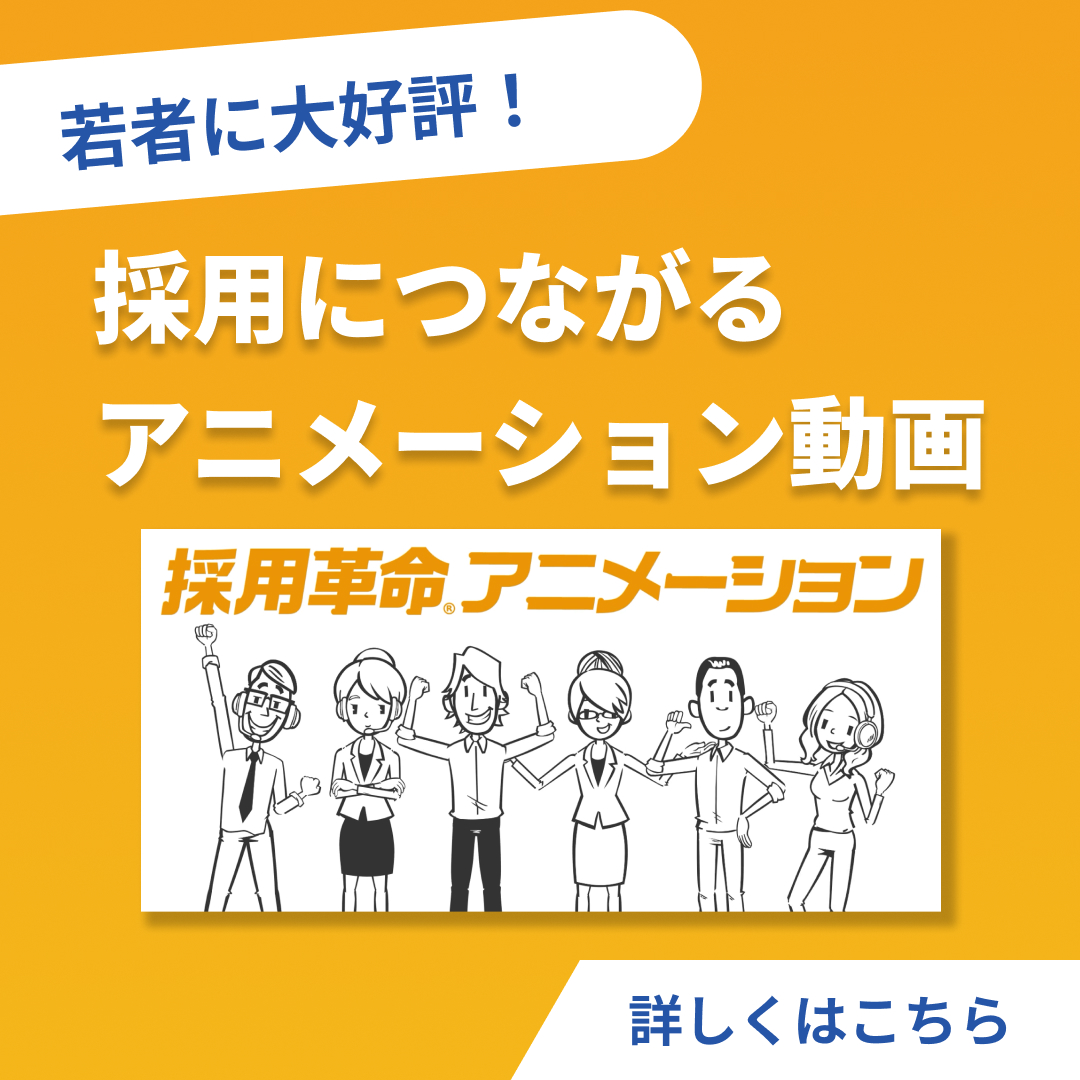

採用革命®アニメーション編集部
年間400本以上の動画制作実績を誇る採用革命®アニメーションの編集メンバー。動画を使ったマーケティングについて、老舗広告会社の視点から解説します。


