
「新卒者が退職代行を利用するケースが増えている?」
「せっかく採用したのに、すぐ辞められたら意味がない」
新卒社員の入社初日から、退職代行を利用するケースが相次いでおり、危機感を覚えている企業の採用担当者も多いでしょう。
背景には、雇用条件の相違や説明不足、人間関係のトラブルなど、いわゆる「入社後ギャップ」が大きく関係しています。
本記事では、若手人材が退職代行を選ぶ理由を深掘りしつつ、企業側が受けるダメージや、退職代行に頼られない環境づくりのために企業が取るべき対策を具体的に紹介します。
1.入社初日から退職代行の利用者が後をたたない事実
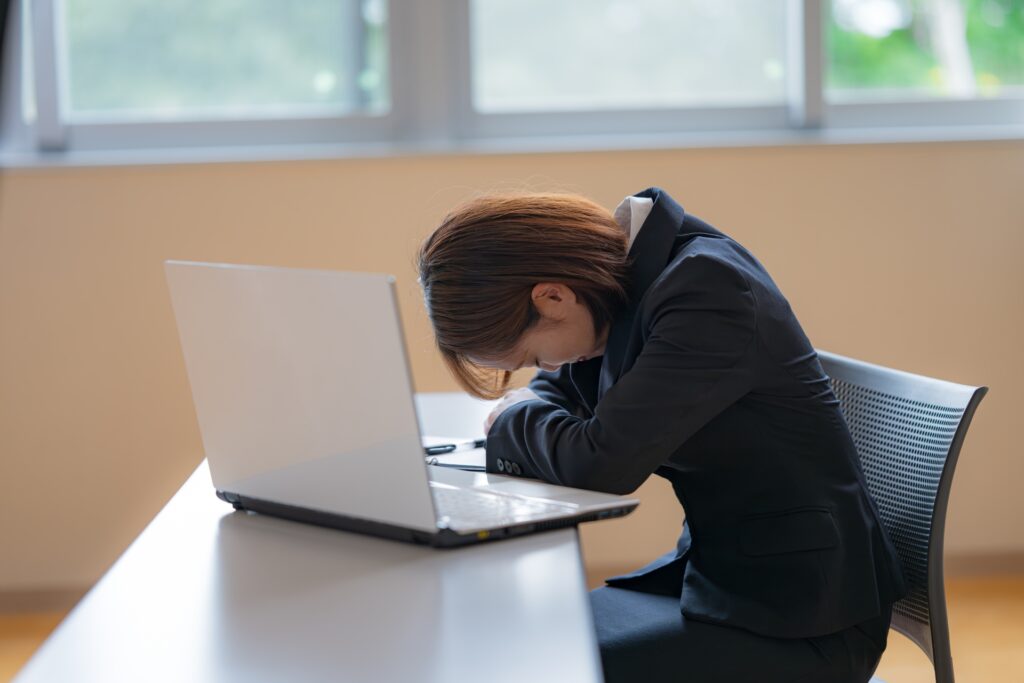
退職代行サービスを提供する「モームリ」のXでの発表によると、2025年新卒者46名から退職代行依頼の申し込みが来ているそうです。
2025年4月1日からの退職代行利用者の依頼数
- 4月1日…5名
- 4月2日…8名
- 4月3日…20名
- 4月4日…13名
4月1日時点でも5名、その次の日からは続々と利用者が増えています。
例年ではゴールデンウィーク明けに利用者が増える傾向にありましたが、2025年はさらに早期化しているようです。
退職動機はさまざまですが、新卒者が語る退職動機には以下のようなものがあることがわかります。
退職代行を利用した理由
- 『入社後に休日出勤の必要があると説明を受けた。入社前はそのような説明は一切受けていなかった。(女性・教育関連)』
- 『思っていた接客業務と違い、やりがいを感じる機会がないと感じた。(女性・飲食業)』
- 『入職前の研修がありマナーやコミュニケーションなどの5時間ほどの研修で講師の方の脅しのような言葉、看護学生と社会人は違うとの言葉があり自信を無くしてしまった。(男性・医療関連)』
まとめると、多くの新卒者が「入社前と、入社後のギャップを感じた」ことが理由で、退職代行の利用を決意しています。
2.新卒者が退職代行を使うのは「入社後ギャップ」だけ?

新卒者が退職代行を利用した理由は「入社後ギャップ」だけなのでしょうか。
さらに詳しく、退職代行利用の理由を紐解いていきましょう。
- 雇用条件や配属部署が聞いていた内容と違う
- 人間関係のトラブル
- 相談できない環境
(1)雇用条件や配属部署が聞いていた内容と違う
退職代行を利用する理由は、雇用条件や配属部署が、事前説明と違うことです。
これらの条件は新卒者がその企業を選ぶ理由の1つであり、その条件が異なれば「この企業で働きたくない」と思ってしまうのも頷けます。
(2)人間関係のトラブル
次に多いのが、人間関係のトラブルです。
配属された部署で人間関係がうまくいかなかったり、同期と揉めてしまうと会社に居にくくなります。
特に同じ部署でトラブルが起きた場合は、その人と距離を空けるのも難しく「自分が辞めよう」となることが多いでしょう。
(3)相談できない環境
頼れる上司がいないなどの環境が、新卒者を退職代行という最終手段に追い込んでいる可能性もあります。
入社後ギャップや人間関係の悩みを誰にも相談できず、最終的に「会社へ行きたくない、辞めたい」と考えてしまうのです。
特に新卒者はまだ人間関係が希薄なので、相談相手がいないと感じやすいでしょう。
このように新卒者が退職代行を利用するには、正当な理由があります。
「若者は退職代行を使ってすぐに逃げ出す」と否定的に捉えず、企業側も自社の問題点や課題を見つめ直し、改善する努力が必要です。
3.退職代行は逃げ?若者の価値観とは

退職代行というサービスを知らずに働いてきた人から見ると「退職代行は逃げだ」と感じるかもしれません。
しかし重要なのは、若い働き手の価値観を理解して寄り添う姿勢です。
- 仕事とプライベートのバランスを取りたい
- SNSのシェア文化により「辞め方の選択肢」が広がっている
(1)仕事とプライベートのバランスを取りたい
日本には「1つの会社には3年は勤めるべき」「風邪くらいで仕事を休むのは根性がない」などの、ある種根性論的な働き方への考え方がありました。
しかし、今はその考えは買い手市場の時代のものであり、今は古いものとなっています。
現在の若者は「仕事や職場は選べるものだ」「プライベートも仕事もどちらも充実させたい」という価値観を持っています。
昔のように入社したら退職まで働くのが当然という価値観がないことは、理解しておかなければなりません。
(2)SNSのシェア文化により「辞め方の選択肢」が広がっている
SNSの発達により、仕事を辞める方法の選択肢が広まったのも退職代行が流行した理由でしょう。
たとえば一昔前までは、退職の連絡は面談でおこなうのが当然でした。
しかし、影響力のある経営者が「退職連絡はLINEでよい」と発信したり、退職代行利用者がその感想を投稿することで、多くの人がいろいろな『辞め方』について知ることができます。
また、SNSが免罪符のような機能を果たしているのも事実です。
たとえば退職代行の利用に多少の罪悪感を感じているとしても、SNSには退職代行の利用を推奨し、「企業側が悪いんだ」と他責的な投稿をしている人も多いです。
このような投稿が背中を押す結果となり、退職代行を利用して簡単に辞めてしまう人が増えています。
4.新卒者の退職代行利用で企業が受けるダメージ

新卒者が退職代行を利用した際に、企業がどのようなダメージを受けるのでしょうか。
改めて企業側の損失について考えてみましょう。
- 採用コストや教育投資のロス
- チーム内での不信感やモチベーションの低下
- 会社の評判を拡散されるリスク
(1)採用コストや教育投資のロス
新卒者が退職代行を利用して早期離職した場合は、採用コストや教育投資が無駄になります。
企業は新卒者の採用のために多大なコストをかけて採用を実施し、さらに入社後は教育のために時間と費用をかけています。
仮に新卒者が4月1日に退職したとしても、それまでの採用コストは全て無駄になってしまうでしょう。
(2)チーム内での不信感やモチベーションの低下
新卒者が退職代行を利用すると、周囲が会社に不信感をもったり、モチベーションが低下したりします。
「こんなに早期退職するなんて、うちの会社何かおかしいんじゃないだろうか」と感じてしまうからです。
また、新卒者のサポートをしていた社員が責任を感じ、モチベーションが落ちるリスクもあります。
(3)会社の評判を拡散されるリスク
退職代行を利用した新卒者により、会社の評判が拡散されるリスクもあります。
最近の若者は自分の窮状をSNSで投稿することが当たり前の文化であり、かなり踏み込んだ内容をSNSに投稿することも。
たとえば「上司がパワハラ気味で、退職代行を使った」とつぶやかれ、会社が特定されれば、瞬く間に拡散され、炎上するリスクがあります。
仮に退職者に問題があったとしても、企業がそれをインターネットで告発し、釈明するのは難しいです。
若者の機嫌を取る必要はありませんが、SNSで晒されるような問題がないかどうかを考えて、リスクを管理していかなければなりません。
5.新卒者が退職代行を選ぶ必要がない環境づくりのコツ

企業が取り組むべきは若者の機嫌取りではなく、退職代行を選ばなくても良い環境づくりです。
具体的にどのようなことに取り組めば良いのか、それを解説します。
- 入社前に企業のリアルを伝えるコンテンツを配信する
- 徹底したコンセンサスの形成
- 配属後のフォロー体制を整える
(1)入社前に企業のリアルを伝えるコンテンツを配信する
新卒者が入社後ギャップを感じないよう、事前説明の方法を考えましょう。
入社後ギャップは企業の説明不足だけでなく、まだ社会に出たことがない新卒者側の解釈が異なることによっても発生します。
働き方や労働条件、仕事内容についてイメージしやすいように、アニメーション動画を配信したり、LPで情報を確認できるようなコンテンツがおすすめです。
特にアニメーションは見る側に情報が伝わりやすい媒体と言われており、文字だけの資料の数千倍の情報を短時間でも伝えられるといわれています。
自社で採用のためのLPを作成し、そこにアニメーションでさまざまなジャンルについての動画を配信するなど工夫して、入社後ギャップを防ぎましょう。
(2)徹底したコンセンサスの形成
新卒社員との徹底的なコンセンサス形成も重要です。
コンセンサス形成とは
- 意見の違いを尊重しながら、最終的に全員が納得して協力できる体制を目指すプロセス
配属部署や仕事内容について事前説明をするのはもちろん、配置転換などがある場合にも説明を実施し、合意を得るようにしましょう。
新卒者が「聞いてない」と思うことがないように徹底するのがコツです。
「言わなくても伝わるだろう、察してくれるだろう」と思わず、丁寧すぎるくらいに合意を取るように心がけましょう。
(3)配属後のフォロー体制を整える
配属後のフォロー体制も構築しておきましょう。
新卒者はまだ人間関係ができておらず、悩みや不安を打ち明ける先がありません。
そのままの状態が続くと「辞めるしかない」と思い詰める可能性があります。
配属後にも丁寧なフォローをするためには、メンター制度や1on1での指導体制などを構築すると良いでしょう。
また、定期的に新入社員に対してヒアリングを実施したり、目安箱を用いて入社後ギャップや不満がないかを聞き取るのも大切です。
なお、意見を聞いただけで放置すると「意見を言っても意味がない」と思われてしまいます。
意見が必ずしも正しいとは限らないので、意見を精査して改善できる場合は実施し、改善できない場合はきちんとその旨を伝えるのが大切です。
6.入社後ギャップを起こさない会社紹介動画なら「採用革命®️」にお任せ

新卒者が退職代行を利用する理由で最も多いのが、入社前の説明とその後のギャップを感じたからです。
そのためには、従来型の大人数の説明会やテキスト主体の資料では不十分かもしれません。
今新卒者に必要なのは、アニメーション動画など若者が親しみやすく、短時間でも情報量を多く伝えられる媒体での会社や業務内容の説明です。
また、LPを充実させて若者がいつでも会社の情報を得られる環境作りも重要です。
採用革命®️では、アニメーション動画の制作やLP制作で、中小企業の採用活動を支援しています。
新卒者が必要な情報を得るためのLP制作、入社前から具体的に入社後の業務や働き方をイメージするためのアニメーションは、入社後ギャップを減らすのに有用です。
採用後長く一緒に働ける人材を採用するためにも、ぜひ弊社サービスをご利用ください。
まとめ
入社初日から退職代行を利用する新卒社員が後を絶たない現実は、企業側の「入社後ギャップ」への向き合い方に問題があるケースが多いです。
雇用条件や配属先の説明不足、相談できない環境といった要因が、新卒者を早期離職へと追い込んでいます。
企業がすべきことは、若者の価値観に歩み寄り、誤解を生まない情報発信と丁寧なフォロー体制を整えること。アニメーション動画やLPを活用したリアルな企業紹介は、その第一歩です。
新卒者の早期離職を防ぎ、長く働いてもらえる環境を作るために、今こそ採用活動の在り方をアップデートしていきましょう。
Z世代の採用につながるアニメーション動画の制作・運用なら「採用革命アニメーション®」
採用革命アニメーションは、今年で創業65年目の広告会社である株式会社JITSUGYOが運営する採用に特化したアニメーション動画制作サービスです。
アニメーション制作は参入障壁が低く、社歴が短い会社やシェアオフィスで運営している会社が多いのが現状です。そんな中でも、弊社は2023年で66期目になり一般企業だけでなく、国や地方自治体、大学、著名人といったお客様との取引も多数ございます。
65年以上続く広告会社であり伝えることのプロだからこそ、誇れる実績が多数ございます。65年以上続く広告会社だからこそできる圧倒的なシナリオ作成力で、営業から取材、制作、広告運用まで一気通貫したサービスをご提供いたします。
アニメーションは作って終わりではなく、その後の採用に対して、認知拡大やマーケティング部分までサポートできるのが弊社の魅力です。Google広告公式認定資格保持者も社内に在籍していますので、専門的でより効果的な施策を実施することが可能です。
採用につながるアニメーション制作をご検討中の企業担当者様は、株式会社JITSUGYOが運営する採用革命アニメーション®に、ぜひ一度ご相談ください。
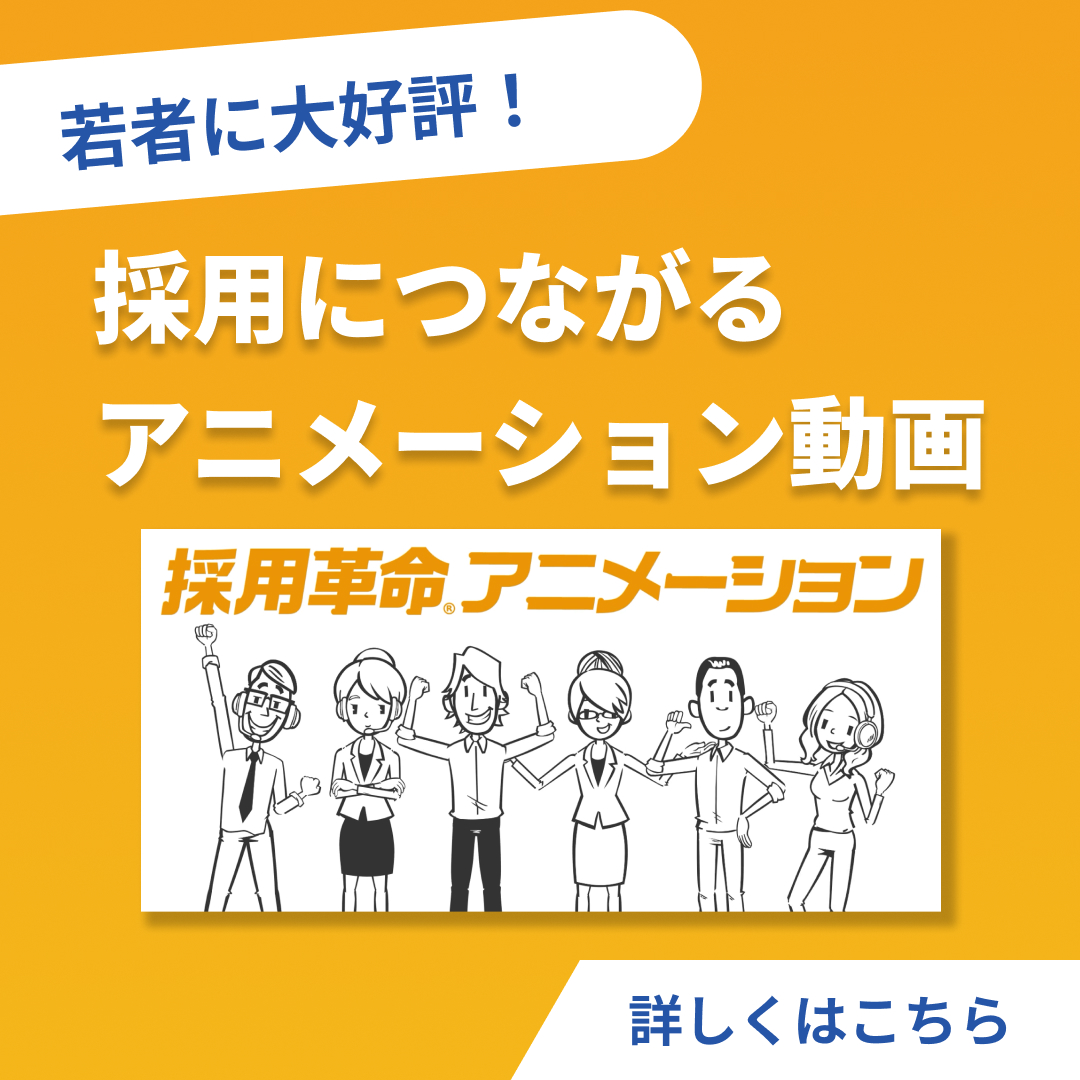

採用革命®アニメーション編集部
年間400本以上の動画制作実績を誇る採用革命®アニメーションの編集メンバー。動画を使ったマーケティングについて、老舗広告会社の視点から解説します。



